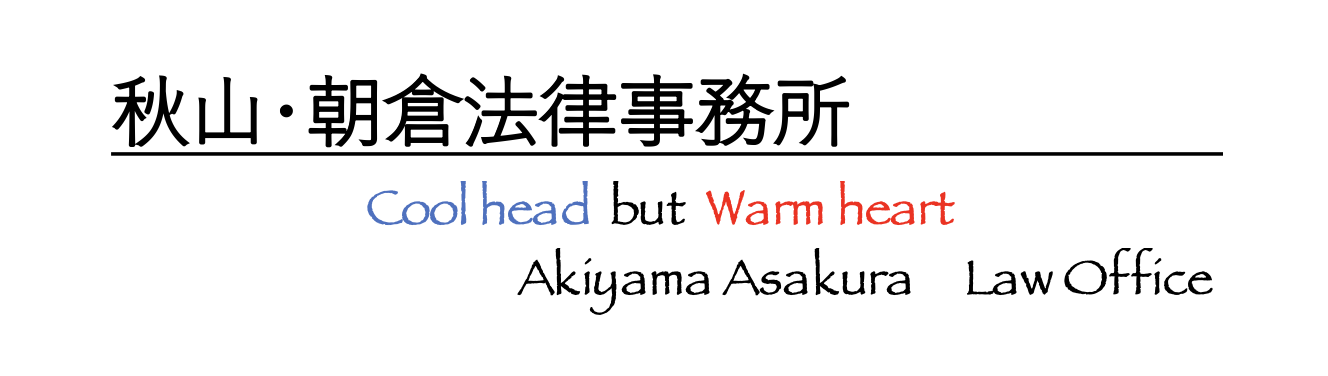建物内の自殺と不動産取引
1 はじめに
近年不況に伴い自殺者数が急増しております。また、老化社会に伴い一人住まいのお年寄りの自然死も増えています。
そこで、今回は、このような物件であることが後に買主に判明した場合に、買主は売買契約を解除し又は損害賠償請求をできるのか、についてご説明したいと思います。
2 買主による契約解除、損害賠償請求の可否
(1)瑕疵担保責任について
買主が当該物件の売買について解除、損害賠償請求をする場合の法的根拠としては、瑕疵担保責任(民法570条)が考えられます。
瑕疵担保責任とは、
①「瑕疵」(目的物が通常有している性能を欠く状態)が契約成立前から存し、かつ②その「瑕疵」が「隠れたる」(契約時に通常の注意義務を尽くしてもその瑕疵を発見できない場合)ものであるときに、生ずる責任です。例えば、売買目的の建売住宅が欠陥住宅で、かつ売買時にも外見上はその欠陥が分らなかった場合が典型例です。
責任の内容としては、その瑕疵による目的物の価値の減少分については、損害賠償請求でき、また、瑕疵によって契約の目的を達成できない場合には契約を解除することもできます。
(2)「瑕疵」にあたるか
本件で問題となるのは、まず、上記欠陥住宅例のような物理的欠陥は誰の目から見ても瑕疵にあたることは明らかですが、本件のような自殺・病死の例については、これを気にしない人もいれば気にする人もいます。そこで、このように人の感じ方によって瑕疵となるか瑕疵とならないかが違ってくるようなケース(「心理的瑕疵」といいます。)でも、瑕疵担保責任の「瑕疵」に該当するのかという点です(なお、ここにいう心理的瑕疵のケースでは、建物での死体の発見が遅れたので建物から死臭が取れない等の「物理的瑕疵」がない場合をいいます。物理的瑕疵については当然「瑕疵」にあたります。)。
この点、判例は、自殺・殺人事件があったという心理的瑕疵も「瑕疵」にあたり得ると判示しています(ケースバイケースですのでもちろん「瑕疵」にあたらないと判断された場合もあります。)。
他方、単なる自然死、病死については一般に瑕疵にあたらないとしています。
判例は、「瑕疵」にあたるかの判断基準について、心理的瑕疵の場合は、買主の個人的感情といった主観的事情ではなく、客観的に建物が通常有する「住み心地の良さ」を欠いている状態にあたるかで判断すべきだとしています。そして、建物が通常有する「住み心地の良さ」を欠くか状態か否かは、以下の事情を総合評価して、「人の死亡にまつわる忌わしさが当該物件から相当程度薄らいでいるか」で判断されるものとしています。
(ア)死体の数、死体の状況
死体の数が多いほど、また死体の発見状況が、首吊り自殺、割腹自殺又は一家惨殺殺人事件であったり、死体発見が相当程度遅れていた場合等、死体発見の状態が忌わしいほど瑕疵該当性は肯定され易くなります。
逆に、自殺が睡眠薬の服用であったり、自殺後直ぐに病院へ運ばれた場合等の場合は肯定され難くなります。
前記病死や自然死が一般に否定されるのもその「忌わしさ」が低いからです。
(イ)死体の存在した場所
死体の存在した場所が、寝室やリビング等の人の日常生活空間であれば肯定され易くなります。
逆に、複数人が出入りするマンションの階段・廊下については通常否定されるでしょう。離れの物置等についても居室等よりは否定され易くなります。
(ウ)死体発見時からの期間の経過
年数が経過すればするほど過去の事実となってその忌わしさも軽減されます。事案にもよりますが判例は6・7年経過した物件について忌わしさを軽減する一事情としています。
また、いったん他の人に貸してその間大過なく過ごして引っ越したのならば、これも忌わしさを軽減する要素になります。逆に、当該自殺等の事情にまつわる嫌悪感から引っ越したのであれば忌わしさを肯定する事情になってしまいます。
(エ)建物の物理的状況
建物内に血痕や髪の毛等死体の痕跡が残っていると、忌わしさを肯定する重大な要素になってしまいます。逆に、当該建物を一度更地にし、建て直した等の事情があれば、原則として、心理的瑕疵には該当しないでしょう。
(オ)購入目的
購入目的が居住目的ではなく営業目的、事務所目的、倉庫目的であれば瑕疵該当製は否定され易くなります。
(カ)売買価格
売買価格が低く抑えられており、自殺等の事情がきちんと価格に反映されていれば瑕疵該当性は否定され易くなります。
(キ)地域
当該地域が人の出入りが多い都市であれば、自殺等の噂も比較的早くなくなるでしょう。逆に、出入りがほとんどない田舎であったりするとその噂もなかなかなくなるものではありません。このような理由で、判例は当該地域の人の出入りの多さや地域社会の密接度等も考慮しています。