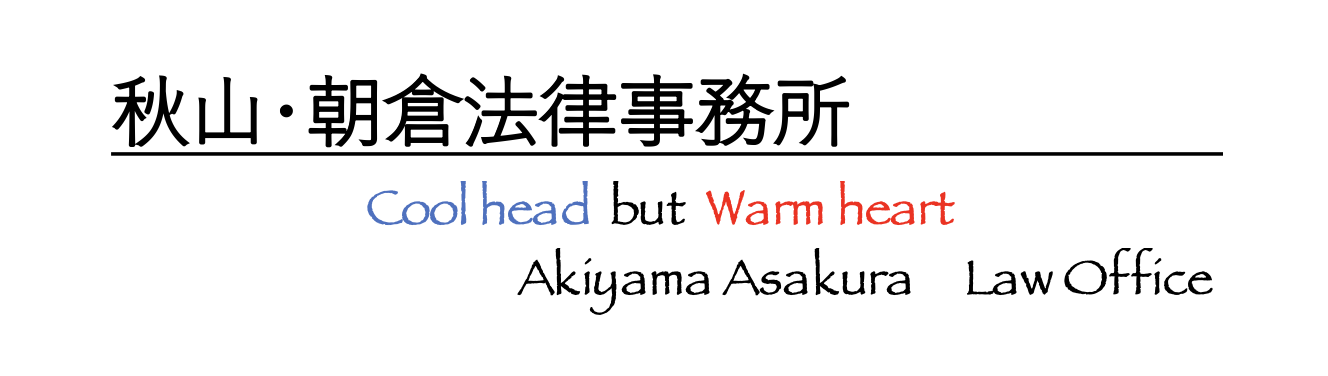ツイッター上の発言と法律問題
<質問>
近時、著名人のAさんがTwitter上で「あ~B殺してえ。」などと、ある著名人Bさんを名指しで攻撃するツイートを繰り返したことで問題になりました。
このようなツイッター上の発言を理由に、Bさんの立場として、Aさんに対し、民事上の損害賠償請求や刑事上の脅迫罪、名誉毀損罪の刑事罰を求めることは可能でしょうか。
<回答>
1 本件のような事案では、仮にBさんがAさんを訴えようとした場合には、民事上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることが可能と考えられます。
たとえツイッターというインターネット上の発言であっても、ある人物を特定した上で「殺してえ」という発言をすることは、社会的に許容される発言の範囲を大きく逸脱しておりますし、名指しで発言された本人においても、このような不当な発言をされたことを受忍しなければならないような理由はありません。
インターネットというのは不特定多数の人が見る「公的な広場」という側面がありますので、そのような場で上記のような発言を一方的にされた場合には、その人の名誉感情を著しく害することは明らかであると言えます。
ツイッターという場は、ついつい日常の会話と同じように発言しがちですが、その発言内容は全て記録に残っているものであり、一般の人にも公開されている発言ですので、そのことを十分に肝に銘じておく必要があると思います。
以上ご説明しましたとおり、本件については名誉感情の侵害による民事上の損害賠償請求は可能と考えられます。
2 もっとも、「殺してえ」という発言について、刑事上の脅迫罪や名誉毀損罪に問えるかというと、そこまでは言えないように考えられます。
(1) まず、脅迫罪における「脅迫」とは、人の生命、身体、名誉等に対する害悪を告知することでるが、本件の発言については、あくまでもツイッターという公開されたインターネット上の発言であり、また、Aさんという著名人が身分を明かした上での発言ですので、このような発言をする方も又受け止める方も実際に「殺される危険がある」とは感じないのが通常でしょう。本件のような場合における「殺してえ」の発言の真意は、「実際に殺したい」という意味ではなく、「そのように思うくらいBさんのことが気に入らない」という意味と捉えられるからです。
ただし、ツイッター上の発言であっても、受け止める方において「実際に殺される危険がある」と受け取られるような態様で発言をすれば、発言者において実際には殺すつもりなど全くなくても脅迫罪に問われる可能性は十分にありますので、注意が必要です。本件はAさんとBさんという著名人の間の発言ですので、むしろ例外的な場合と考えた方がよいでしょう。
(2) 次に、名誉毀損罪における「名誉毀損」とは、①不特定多数の人に対し、②事実を摘示することによって、③人の社会的評価を低下させる行為を言います。
本件については、「殺してえ」というAさんの心情を述べたに過ぎませんので、Bさんの「社会的評価を低下させるような事実」を示したものではありません。
(3) したがって、本件のような事件であっても、刑事上の脅迫罪や名誉毀損罪には問うことはできないと考えられます。