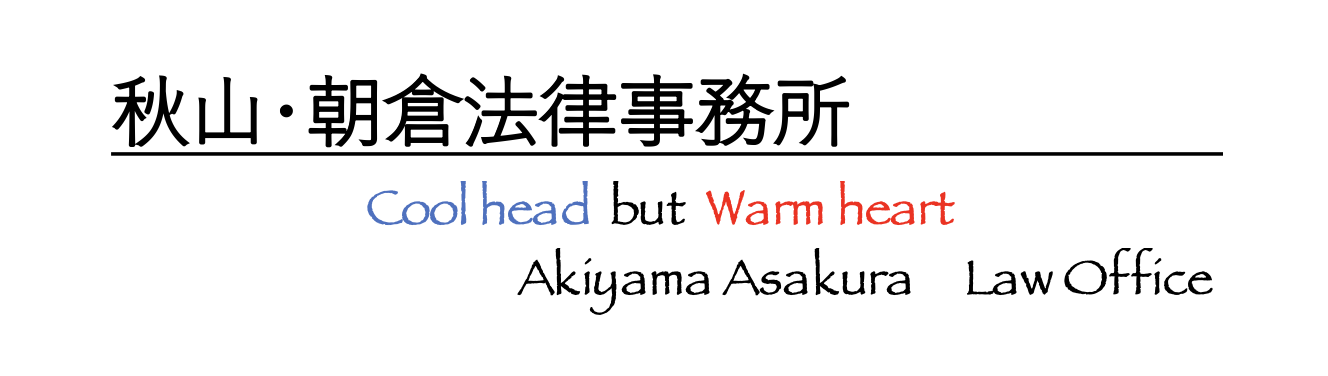建築協定の拘束力
<質問>
私は、ある不動産業者から宅地を購入し、木造3階建ての建物を建設中です。ところが、近隣の方からこの地区は、建築協定によって建物は2階建てまでの建物に限定されており、3階建て以上の建物を建設できないと言われました。しかし、私は、宅地を購入する際にこのような建築協定のことについては一切説明も受けておりませんし、建築協定に署名捺印などもしていません。建築協定に拘束力などあるのでしょうか?
<回答>
建築基準法69条以下では、建築協定に関する制度を規定しております。
建築基準法は、建物の安全性や良好な住環境を確保するため、最低限の建築基準を設けて建物の建築について規制している法律ですが、良好な住環境の確保の観点からは、それぞれの地域の特性を生かした決め細やかな規制を行いたいという場合もあるでしょう。
そこで、建築基準法69条以下では、市区町村が条例で定めた一定の地区に関しては、当該地域の所有者および借地権者(以下「地権者等」という)の全員の合意のもと、建築協定書を作成し、市区町村の長に提出して、市区町村長の認可、公告の手続きを経ることで、地権者に対し効力を発生する建築協定の制度を設けております。
建築協定は、上記の市区町村長による認可と公告の手続きを経ていれば、その後に当該地区の所有権や借地権を取得した者がいたとしても、その者に対しても当然に効力を生じます。土地の取得者が建築協定の存在について知っていたかどうかは問われません。
したがって、本件については、当該建築協定が上記の認可、公告の手続きを経ているかどうかを確認し、もし上記の手続きを経ている場合には、3階建ての建築計画を2階建てに変更する必要があります。建築協定を無視して、3階建ての建物を建築した場合には後に3階部分に関しては、建築協定違反として撤去を求められることになるでしょう。
そして、このような建築協定の存在は、重要事項説明事項として当然に調べておくべき事項ですので、建築協定の存在を説明しなかった不動産業者に対して、あなたは説明義務違反による損害賠償の請求ができます。
もっとも、建築協定は、地権者等の過半数の合意によって、市区町村の長に廃止の申請をすることができ、市区町村の認可を受ければ廃止することもできます(建築協定の変更の場合には全員の同意が必要です)。そこで、建築協定が古く、その地区の実情にふさわしくなくなってきた場合には、3階建て以上の建物の建設を禁止する本件の建築協定について当該地区の地権者の過半数の同意を経た上で廃止の申請をすることも検討されてよいかもしれません。
上記の廃止の見込みもなく、また、3階以上の建物を建設できないのでは、土地を購入した意味もないというのであれば、不動産業者に対して、土地の売買契約の取り消しを請求できる場合もあります。
消費者契約法では、消費者は、事業者に対して、①事業者の不実告知または②不利益事実の不告知を理由に、契約の取り消しを請求できます。
①の不実告知とは、本件では2階建ての建物しか建設できないのにもかかわらず、3階立の建物が建設可能だと称して、3階建ての建物の建設請負プランを設定して、土地の売却の広告をしている場合などです。
②の不利益事実の告知は、事業者が重大な不利益事実を知っていながら、告知しなかった場合に取り消しができるものです。本件の建築協定は、土地の利用に関する重大な制限ですので、重大な不利益事実に該当することは明らかです。しかし、仮に事業者も建築協定の存在を知らなかった場合には、不利益事実の不告知による取り消しはできませんので、建築協定の存在を売買契約時までに不動産業者が知っていたか否かが争点になることが予想されます。