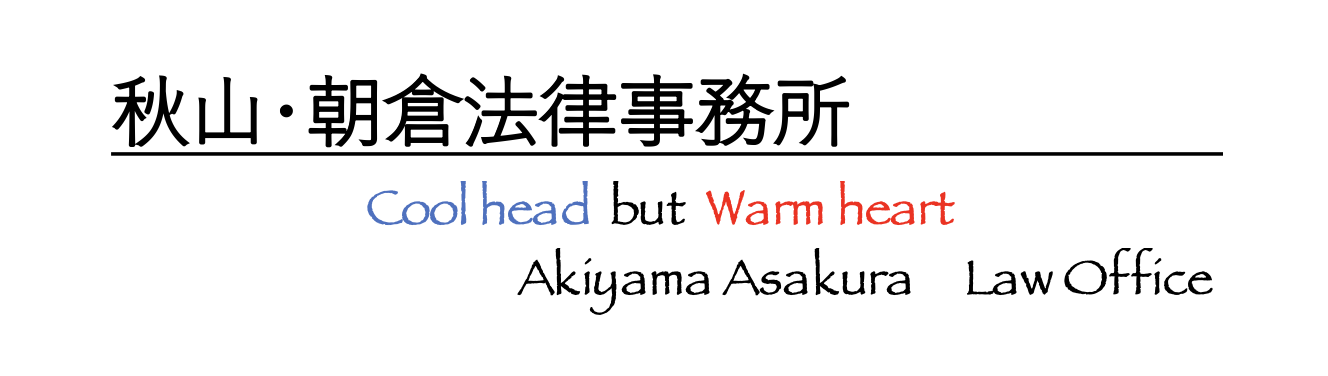遺留分の放棄に関する法律相談
<質問>
私は、ある不動産賃貸業の会社を経営しており、いくつかの不動産を保有しております。
妻は既に他界しておりますが、子どもが二人おります。長男は会社の経営を手伝い、次男は海外で悠々自適に暮らしている状況です。
長男に会社を引き継がせるため、次男には一定額の預金を渡すことで、会社の株式とそのほかの不動産等の財産については、長男に相続させることを考えております。
幸いにして次男もその考え方に了解してくれています。しかし、将来のことを考えると、次男にしても考えが変わるとも限りませんので、きちんとした法的な手続きを取っておきたいと思います。
どのような手続きを取ればいいのでしょうか。今のうちに、次男から相続放棄の書面に署名・捺印をもらっておけばよいのでしょうか。
なお、これまでに長男・次男に生前贈与したことはありません。
<回答>
1 被相続人の生前に相続人が相続放棄の書面を作成していたとしても、生前の相続放棄は無効とされております。
そのため、本件のように被相続人の生前において相続財産の分配方法を確定しておきたい場合には、あらかじめ遺言書を作成しておいて、相続財産の分配方法を具体的に定めた上で(例えば、預金Xは次男に、その他の遺産は全て長男に相続させる)、次男においては遺留分放棄の許可の申立(民法1043条)を家庭裁判所にして、家庭裁判所から許可の審判を得ておく必要があります。
家庭裁判所は、次男において遺留分の放棄の意思表示が真意に基づくものか、その他遺留分放棄に至った事情を考慮して、許可の審判をします。
2 もっとも、生前における遺留分の放棄が意味をなすのは、遺言による相続財産の分配方法が遺留分を侵害する場合です。本件における次男の遺留分は、これまでに生前贈与をしたことはないとのことですので、相続財産から相続時の負債額を差し引いた金額の4分の1(=1/2×1/2)です。
したがって、遺言によって次男に渡す予定の預金額がこの遺留分額を下回らなければ、遺留分を侵害することはないので、遺言書を書くだけで足ります。
本件のように不動産を多数お持ちの場合には、不動産の価値がかなり高額となる場合が多いでしょうから、一定額の預金を渡してもなお遺留分を侵害するとされるケースが多いでしょう。生前における遺留分の放棄の許可の手続きを取るべきか否かは、この点を考慮して決めることになります。
3 このほかに「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」では、会社の事業承継にあたって、後継者が議決権の過半数を確保することできるよう、株式等の生前贈与が行われた場合の遺留分に関する民法の特例が設けられております。
これは、一定の要件を満たす中小企業においては、旧代表者の推定相続人全員の合意により、旧代表者から後継者に生前贈与された株式等を①推定相続人の遺留分算定の基礎財産から除外する、または、②後継者が贈与を受けた株式等の評価額を一定額に固定する合意がなされ、その合意内容について家庭裁判所の許可を受けることにより、当該生前贈与を受けた株式等に対する遺留分の行使を制限できるというものです。
②は、株式等の生前贈与が為された後、後継者の経営努力によって株式の価値が上昇したという場合に、遺留分算定の際の株式の評価額は相続開始時を基準とされていることの不公平さをなくすための制度でもあります。
民法の制度は、遺留分の放棄という制度であり、遺留分権者にとってはオールオアナッシングの制度のため、かえって使いにくいという難点がありましたが、上記制度は、事業承継に必要な株式に関してのみ適用される制度ですので、遺留分を全部放棄してしまう民法の制度に比べて中間的な方法として利用が期待できます。