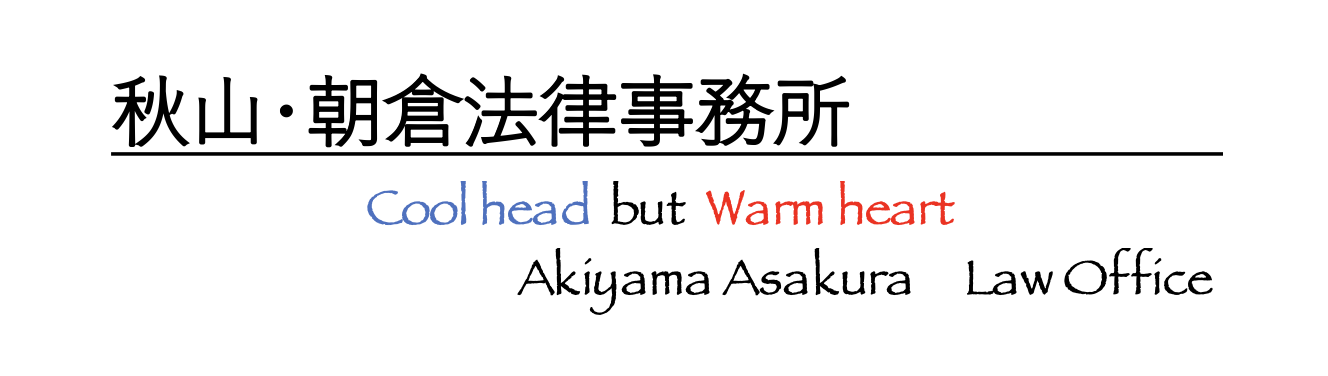定期借家権
1 はじめに
既に存知の方も多いとは思いますが、平成11年12月、「良好な賃貸住宅等の供給の促進」を目的とし、借地借家法が一部改正され(平成12年3月1日施行)、新たに「定期借家権」という制度が成立しました。
従来は、一度建物を賃貸すると、家主は、借地借家法上の「正当事由」がないと更新拒絶ができないとされ、また、その「正当事由」の認定も多くのケースで立退料が必要であるなど大変な厳格な要件であった為、建物を貸すことをためらわれる家主が多くおりました。
特に、「期限を限定してその期間だけ貸した後は無条件で建物を返してもらいたい」という家主にとって、従来の借地借家法はいくぶん借家人保護に厚すぎたた面があったため、使い勝手の悪い法律になっていたと言えます。
今回の改正法は、「賃貸期間の経過後は無条件で建物を返してもらいたい」という家主でも、ためらうことなく建物を貸し出すことができ、結果的に、「良好な賃貸住宅等の供給が促進」されることを期待して制定された法律です。
ただし、借家人にとっては、更新ができない、途中解約が制限されるというデメリットもありますから、借家人側の仲介をするときは、このれらの点についての十分な説明が必要です。
そこで、今回は、今後ますます利用されるであろう定期借家契約について、不動産業者として最低限押さえておくべきことをご説明したいと思います。
2 定期借家契約の形式と手続き
定期借家契約では、借主保護の要請から以下の3つの手続きをふむをことを貸主に義務付けています。これらの手続きを一部でも怠ると更新可能な通常の借家契約となったり(後記①②)、直ちには契約終了が認められなかったり(後記③)するので注意が必要になります。
①書面によって契約をかわすこと
定期借家契約では、契約時に「公正証書等の書面」によって契約をすることが必要です。
この契約書には、「期間の満了とともに契約が終了し、更新をしないこと」を明記する必要があります。
なお、契約書の形式ですが、「公正証書」というのは例示にすぎませんので、通常の契約書を交わすだけでもかまいません。
ただし、強制執行受諾文言付き公正証書によることで、将来賃借人が賃料を滞納した場合、裁判をして判決を得ずに滞納賃料に対して強制執行の手続きをとることができます。ただ、この場合にも、賃貸借契約を解除して明渡しを求めるときは、判決等を得なければなりません。
②定期借家権の内容について書面を交付して説明すること
貸主は、契約締結前に「本賃貸借契約では期間の満了をとともに契約が終了し、更新ができないこと」を書面をもって、説明しなければなりません。このような書面の交付による説明を怠った場合も、更新可能な通常の借家契約になります。
なお、上記説明をしたことを証拠に残しておく為に、説明後、借主から説明を受けたことの署名・捺印を得ておくべきでしょう。
③定期借家契約の終了時の通知
期間が満了すれば、それだけで契約が終了するわけではありません。貸主は、期間満了前の6ヶ月前から1年前の間に、「○月○日で期間満了につき本賃貸借契約は終了し、更新はできない」旨を改めて通知しておかなければなりません。
万一、契約終了6ヶ月前の通知を忘れた場合は、通知を出したときから6ヶ月経過後が契約終了時になります。
なお、契約期間が1年未満の借家契約については、上記のような通知は不要です。
3 定期借家契約の効用(主に家主の観点から)
①契約終了時期の予測可能性
貸主にとっては、契約終了時がはっきりしているわけですから、契約終了後の借家の利用を予測して行動できます。
例えば、転勤の間だけ家を貸したい、留学の間だけ家を貸したい、3年後に建物を取り壊す予定だから3年間だけ家を貸したいと言う場合です。
また、商業地の事業用のテナントの場合などには、10年間だけ貸すことを前提に権利金の額を決めることができるなど、利用期間にあわせた権利金の設定が可能になります。
② 長期の定期借家契約も可能
定期借家契約は、民法上の契約期間の上限である20年を超える契約期間でも、もちろん設定可能です(借地借家法29条2項)。今回改正された定期借家権は短期の借家契約だけに限られていませんので、契約期間は自由に設定することができます。
③ 賃料改定の特約
通常の借地借家契約では、賃料増減額請求権が認められておりますので、例え賃料の改定の条項を設けていたとしても、借家人から上記賃料増減額請求権を行使されれば、調停や裁判を経て賃料を減額されるおそれがありました。
しかし、定期借家契約では、賃料の改定の特約を設けたけた場合、この特約を優先させることとし、賃料増減額請求権を認めないことにしました。 従って、家主も借家人も、従来の取決めに沿って賃料の改定を行えるようになりました。ただし、これらの特約は、一度決めた以上拘束力を持ちますので、家主にも不利に働く可能性はあります。特に長期の定期借家契約の場合には、将来の地価高騰やインフレなども十分予測して慎重に決めなければなりません。
もっとも、高ければそれでいいと言うわけではなく、著しく高すぎる法外な賃料改定の特約は、消費者保護法や公序良俗違反、事情変更の法理等でその特約自体が無効とされる恐れがありますので、賃料の増額幅もある程度合理的な範囲内にしなければなりません。
4 その他留意事項
① 借家人からの中途解約権
定期借家契約では、家主からも借主からも解約権を認めないのが原則です。従って、途中解約ができない以上、残存期間の賃料については、使用しても使用しなくても支払わなければなりません。
しかし、借主保護の観点から、「床面積が200平方メートル未満の居住用建物の借家契約」においては、「転勤・療養・親族の介護そのたやむを得ない理由があって、借主が生活の本拠として使用することが困難となった場合」には、借主からの解約権が認められます。
床面積200以上の建物や事業用の借家契約の場合には、途中解約権が認められませんので注意が必要です。中途解約権を留保したい場合は、契約書にその旨明記しておかなければなりません。
② 定期借家契約終了後の再契約の場合
定期借家契約終了後に再び定期借家契約を締結しなければならない場合は、また初めから定期借家契約を締結しなおさなければならず、改めて前記2の①②の手続きを踏まなければなりません。また、定期借家契約には「合意による更新」という概念もありません。
一度定期借家契約を締結しているからといって、上記手続きを怠ると、通常の更新可能な借家契約になってしまいますので注意が必要です。
③通常の借家契約から定期借家契約への切り替えの可否
本改正法施工後、「当分の間」は、通常の借家契約から定期借家契約への切り替えはできないことになっています。これは、借家人保護のための規定です。但し、例外的に、事業用借家契約については、借家人保護の観点は不要ですので、定期借家契約への切り替えも可能です。
「当分の間」とは、条文では明確に何年とは指定しておりませんが、国民一般の間に定期借家権制度が浸透するまでと考えられています。いずれ、この点についての政令ないし附則が出るでしょう。
④定期借地権との違い
以上、定期借家権について説明しましたが、定期借地権については、定期借家権の取り扱いとは必ずしも同じではありませんので注意して下さい。定期借地権については、定期借地権についての条文(借地借家法22条から25条)や参考書を参照してください。