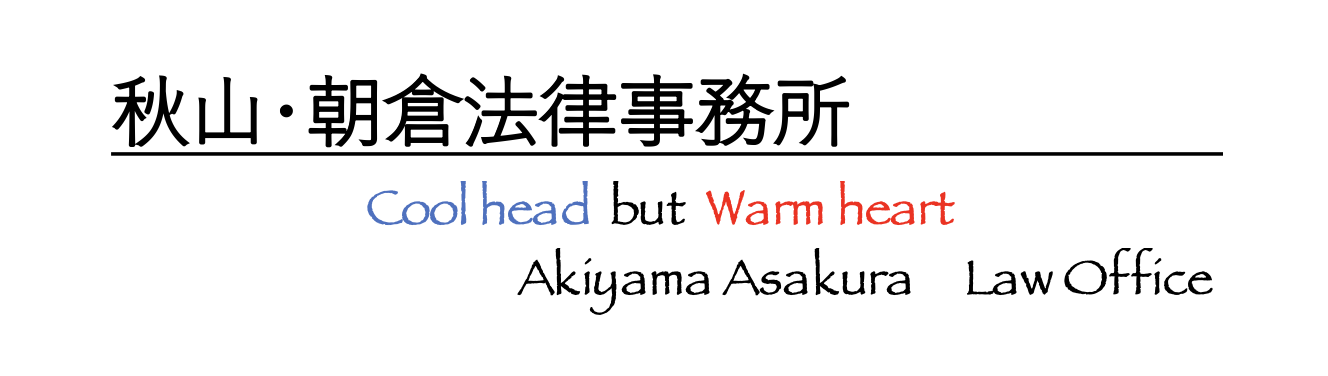借地借家法の改正と定期借地権制度の概要
<質問>
借地借家法が改正され事業用定期借地権の制度が利用しやすくなったと聞きました。どのような点が改正されたのでしょうか。
また,借地借家法で定めのある定期借地権制度の概要を教えてください。
<回答>
1 平成19年の借地借家法の改正について
借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第132号)が公布され,事業用定期借地権を設定する場合の存続期間がこれまでの「10年以上20年以下」から「10年以上50年未満」に改正され,上限が引き上げられました。施行期日は平成20年1月1日です。
これまで事業用定期借地権は存続期間10年以上20年以下の範囲でしか設定できませんでした。
しかし,建物の税法上の減価償却期間は20年を超えるものが多く,これに見合った条件で定期借地権を設定できるようにしてほしいという要望が多く寄せられたため,今回の改正により,存続期間10年以上50年未満の範囲で事業用定期借地権を設定できるようになりました。
なお,存続期間が50年以上の借地権を設定する場合には,その建物所有の目的が事業用であるか居住用であるかを問わず,一般定期借地権(借地借家法第22条)によることができます。
したがって,改正後は,事業用の建物の所有を目的とする借地権については,一般定期借地権と事業用定期借地権を適宜選択することにより,存続期間10年以上の範囲で自由に設定することが可能になりました。
2 借地借家法上の定期借地権制度
借地借家法では,一般定期借地権,建物譲渡特約付借地権,事業用借地権の3種類の制度が定められております。
以下では,誌面の関係もありますので,この3つの制度の概要及び契約上の注意点に関する項目を挙げておきます。
(1)一般定期借地権
一般定期借地権は以下のような特徴をもった契約です。
①契約の更新がなく契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了
②建物買取請求権がない,建物の再築による期間の延長がない
③書面によることが必要
④存続期間は50年以上
⑤契約上の留意点
・原状回義務の範囲を明確にする。
・権利金若しくは保証金の性格を明確にしておく。
・分譲マンションでは借地権譲渡に地主の同意が不要な地上権方式を利用する。
・定期借地権消滅後の建物賃借人の扱い
→借地借家法35条の建物賃借人の1年間の明け渡し猶予,38条の一般の定期借家権制度の利用,39条により建物賃貸借契約で終期を明記することで建物の取り壊し時に建物賃貸借契約が終了する特約などによって,定期借地権の消滅時若しくはそれから1年以内の間に建物賃借人は建物からの退去義務が生じる。
・特約がなければ借地人は期間満了まで中途解約はできない。
・建物無償譲渡特約の有無
(2)建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは,通常の借地契約に,設定後30年を経過した日以降に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた契約です。例えば,契約期間40年の普通借地契約に30年を経過した時から期間満了時までに地主の申し出によって建物が譲渡される特約を付けた契約です。
更新なく借地権が消滅するという点で地主の利益に適い,建物譲渡による投下資本の回収ができ,原状回復義務がないという点で借地人の利益に適うが,実際に契約をするとなると以下のような問題点があり,複雑な契約関係になるため,現在ではあまり利用はされていないようです。
①相当の対価の額をめぐり将来紛争になる可能性がある(契約書では相当な対価をどのように算定すべきかを明確にすることが望ましい。契約書に明確な売買金額を定めておく,複数の不動産鑑定士の鑑定結果によるなど。)
②相当の対価に借地上の「場所的・環境的利益」を考慮するのか否かは見解が分かれるところである(契約書でも上記の点を明らかした方が望ましい。なお,建物買取請求権の場合,借地権価格は含まれないが「場所的・環境的利益」を考慮するというのが判例である)
③無償で譲渡する旨の特約は「相当の対価」との条項に違反し無効
④建物所有権移転登記を保全するための仮登記を設定する必要がある(地主は,譲渡特約に反して第三者に建物が譲渡される或いは建物が競売されると,建物を優先的に譲り受けることによって借地権を消滅させることができなくなる。そのため,譲渡特約による建物所有権移転登記を保全するため第1順位の所有権移転の仮登記を設定する必要がある)
⑤地主による建物譲渡の申出期間の設定の制限の定め(借地人が長期間不安定な地位におかれることを防ぐため)
⑥建物賃借人の扱い
・建物譲渡特約に基づく地主の所有権保全の仮登記前に建物が第三者に賃貸され引き渡された場合で,建物が第三者に賃貸され現に第三者に使用されている場合には,法31条により建物の賃借権が地主が取得する建物所有権に対抗可能となる。そのため、建物賃借人は建物賃借権を従前の借地人に対するのと同様に地主に対し主張することが可能になる。
・建物譲渡特約に基づく地主の所有権保全の仮登記後に建物が第三者に賃貸され引き渡された場合若しくは借地人自身が建物を使用している場合で,借地権の消滅時点において借地人又は建物の賃借人が借地上の建物を現に使用している場合には,法24条2項により,同人らの請求によって地主との間で「期限の定めのない建物賃貸借契約」が成立したものとみなされる。ただし,借地権者と建物賃借人との間で38条1項の定期借家契約が締結されている場合には,それによる契約終了が優先する(24条3項)。「期限の定めのない建物賃貸借」は,貸主からいつでも解約申出ができ,解約申し出時から6ヶ月の経過をもって賃貸借契約は終了するが,解約申し出には「正当事由」が必要になるため,一般の賃貸借契約と同じように貸主側の自己仕使用の必要性と借主側の必要性及び立退料の提供の有無などを総合考慮して判断される。もっとも,貸主側の正当事由として,建物の借地がもともと24条の建物譲渡特約付借地権であったことが考慮されるので,一般の賃貸借契約の場合に比べ正当事由は具備される易くなる(一定期間の立ち退きの猶予若しくは通常よりも少額の立退料の提供で正当事由を具備すると判断される可能性が高い)。
(3)事業用定期借地権
①契約の更新がなく契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了
②建物買取請求権がない,建物の再築による期間の延長がない
③専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)を所有する目的で設定される借地権
④存続期間は10年以上50年未満と拡大された
⑤公正証書による契約が必要
⑥定期借地権消滅後の建物賃借人の扱いは,法35条により建物賃借人が借地権消滅を知った時から1年間明け渡し義務が猶予される。