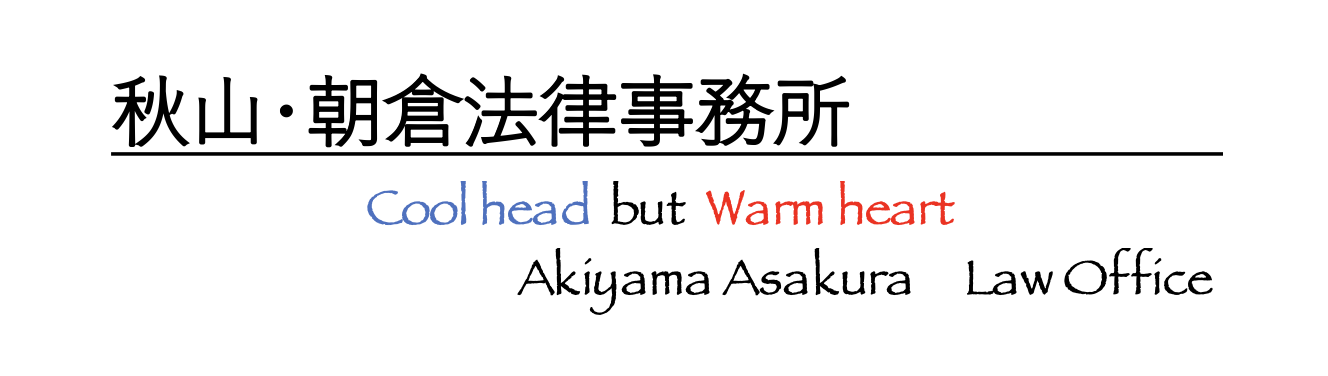消費者契約法第10条の適用により原状回復義務を賃借人負担とする特約を無効とした裁判例
(事案)
Xは、平成10年7月、Yとの間で共同住宅の一室の賃貸借契約を結んだ。 同賃貸借契約には、自然損耗および通常の使用による損耗について賃借人が原状回復義務を負担すること及び賃借人が原状回復義務を負担する場合の回復費用の具体的な単価が記載されていた。
同契約は、消費者契約法が施行された平成13年4月1日のあとである同年7月7日に更新の合意がなされた。
その後、賃貸借契約は解除されたが、Yは、上記特約により、原状回復費用を敷金から控除すると返還される敷金はないと回答したため、Xは、預け入れ敷金20万円の返還を求めてYに提訴した。
以上のような事案で、京都地裁平成16年3月16日判決(最高裁ホームページ掲載)は、
① 消費者契約法施行前に締結された賃貸借契約にも、同法施行後に賃貸 借契約が合意により更新された場合には、更新後の契約に同法の適用が ある、
② 消費者契約法第10条により、自然損耗および通常の使用による損耗 に関する原状回復義務を賃借人に負担させる旨の本件特約は無効である、
と判示し、賃貸人Yに敷金全額の20万円の返還を命じました。
(解説)
1 消費者契約法の施行時期と賃貸借契約の更新
消費者契約法の施行時期は平成13年4月1日です。
法律には不遡及の原則がありますから、法施行日以前に締結された契約には、法の適用がないのが原則です。
しかし、本裁判例は、「消費者契約法の施行後である平成13年7月7日に締結された本件合意更新によって、同月1日をもって改めて本件建物の賃貸借契約が成立したから、更新後の賃貸借契約には消費者契約法の適用がある」としております。
その理由として、裁判例は「実質的に考えても、契約の更新がされるのは賃貸借契約のような継続的契約であるが、契約が同法施行前に締結されている限り、更新により同法施行後にいくら契約関係が存続しても同法の適用がないとすることは、同法の適用を受けることになる事業者の不利益を考慮しても、同法の制定経緯および同法1条の規定する目的にかんがみて不合理である」と判示しており、賃貸借契約の継続性という特殊性に照らして、消費者保護法の趣旨は、更新後の契約にも及ぼすべきだと解釈しております。
本事例は、消費者契約法の施行後に合意更新が為されたケースですが、上記判断理由によりますと、法定更新のように合意によらない更新のケースでも、消費者保護法を適用すべきとの判断を下しているように思われます。この点は、法律の不遡及の原則からすれば、だいぶ思い切った解釈のように思われ、学説上は賛否が分かれるところかもしれませんが、消費者契約法の趣旨を現行の賃貸借契約に反映させる点を特に重視した判決例と言えます。
2 消費者契約法第10条の適用
これまで、事業者と消費者の間には交渉力と情報に大きな格差があるため、消費者が不当な契約を強いられるといった批判がありました。消費者契約法は、この格差を是正し、消費者を不当な契約から守る目的で定められた法律です(消費者契約法の詳細は、本誌第17回で詳しく説明しております)。消費者契約法は、契約当事者の一方が「事業者」で他方が「消費者」である契約に適用されます。
そして、消費者契約法第10条では「消費者の権利を制限し、又は、義務を加重する消費者契約条項であって、民法第1条2項(信義誠実の原則)に反して、消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定めております。
本裁判例では、本事例に消費者契約法第10条を適用した理由として、
①賃借人が、賃貸借契約の締結に当たって、明け渡し時に負担しなければならない自然損耗等による原状回復費用を予想することは困難であること(したがって、本件のように賃料には原状回復費用は含まれないと定められていても、そうでない場合に比べて賃料がどの程度安いのか判断することは困難であること)
②本件の契約書では、原状回復費用の単価は契約書に明示してあるが、建物明け渡し時に具体的にどの部分のどのような面積を原状回復しなければならないのか予測が困難であること、
③よって、賃借人は、賃貸借契約締結の意思決定に当たっての十分な情報を有していないこと、
④本件のような集合住宅の賃貸借において、入居申込者は、賃貸人または管理会社の作成した賃貸借契約書の契約条項の変更を求めるような交渉力は有していないから、賃貸人の提示する契約条件をすべて承諾して契約を締結するか、あるいは契約しないかのどちらかの選択しかできないこと、
⑤これに対し、賃貸人は将来の自然損耗等による原状回復費用を予想することは可能であるから、これを賃料に含めて賃料額を決定し、あるいは賃貸借契約締結時に賃貸期間に応じて定額の原状回復費用を定め、その負担を契約条件とすることは可能であり、また、このような方法をとることによって、賃借人は、原状回複費用の高い安いを賃貸借契約締結の判断材料とすることができること
を挙げ、自然損耗等による原状回復費用を賃借人に負担させることは、契約締結に当たっての情報力および交渉力に劣る賃借人の利益を一方的に害するものといえ、本件原状回復特約は消費者契約法10条により無効であると判示しております。
本裁判例では、特に、建物明け渡し時の原状回復費用がいくらかかるのか、賃借人には、具体的に予測困難であることを重視し、同法の適用を認めているようです。
これまでの裁判例でも、通常の居住用建物の事例における原状回復義務の特約条項(「契約時の原状に復旧」等の文言を使用)の解釈として、原状回復の義務付けられた損害に自然損耗等が含まれないとし、契約条項の制限解釈をした裁判例は、川口簡易裁判所平成9年2月18日判決(消費者法ニュース32号80ページ)、大阪高等裁判所平成12年8月22日判決(判例タイムズ1067号209ページ)他多数があり、裁判例の一般的な傾向にあると言えました。
しかし、本事例のように、明文の条項をもって、自然損耗等についての原状回復義務を賃借人に負担させている場合、契約条項の解釈論としては限界がありました。本裁判例は、そのような中で消費者契約法の適用により正面から「自然損耗等についての原状回復義務を賃借人に負担させる」条項を無効とした点で、注目される裁判例です。
3 本裁判例の意義及び賃貸人としての今後の対応
あくまで下級審レベルでの裁判例であり、最高裁判例とは異なります。 もっとも、最高裁のホームページでも紹介されているところを見ると、実務上は先例としての意義はそれなりに大きいと思われます。
今後、賃貸人側としては、通常損耗や自然損耗について契約書の条文で賃借人負担とすることを明記しても、消費者との賃貸借契約では無効とされる可能性が十分にあることを考えなければなりません。
したがって、賃貸人としは、通常損耗や自然損耗のリフォーム費用については毎月の家賃からの費用回収を前提に家賃設定をすることなどを考えなければならなくなる時代になったと言えるでしょう。
あるいは、上記裁判例の理由⑤で示されているように、消費者契約法第10条が適用されないような契約書の記載方法としては、例えば、通常損耗分等として賃借人が負担する原状回復義務の履行費用を、居住年数に応じて「使用期間1年の場合金○○円」とするなど契約書上明記しておく方法が考えられます。このように負担金額が明記されていれば、消費者は退去時の費用負担を具体的に予測して契約を締結できることになりますから、上記裁判例で強調している①②の理由は当てはまらなくなりますし、上記裁判例でも、このような契約方法であれば、消費者契約法第10条の適用を避けられることを示しているように思われます。
したがって、上記のような方法で退去時の費用負担額を具体的に明示していること、賃借人の負担金額も不合理ではない控え目な金額に止めていること、退去時の費用負担について分かり易い丁寧な説明を履行し確認書を別途取っておくこと、などの契約手続きをとっていれば、消費者契約法第10条により無効とされることもないと思われます。また、退去時のトラブルを避けるという意味でも有意義ではないかと思われます。