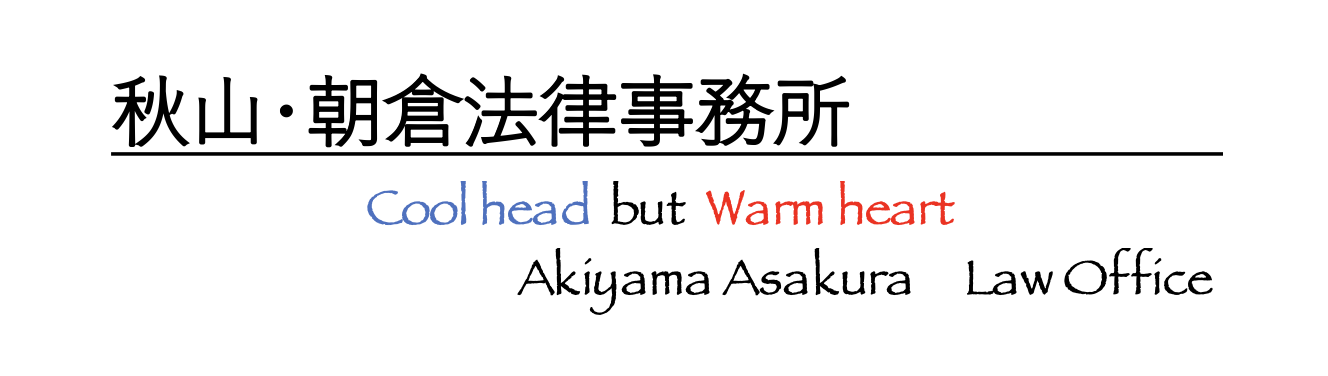袋地の通行権にはどのようなものがありますか
<質問>
私は、土地付の中古建物を購入しました。その物件は、建物からから公道に出ることができる唯一の通路部分は、隣接地の地主が所有している土地なのですが、自由に行き来できるので問題ないと売主Aから説明を受けていました。
しかし、購入後、しばらくすると、その地主が当該通路部分に植木や花壇を造り、公道に出れないようにされてしまいました。
通路部分の地主に植木等を撤去するように言っても、自分の土地だから何をしようと自由だと言って話に応じてくれません。
どうしたらよいのでしょうか。売主に責任追及すべきでしょうか。それとも、まずは、地主に植木の撤去を請求すべきでしょうか。
<回答>
1 この種の事案では、まず、当該通路部分にどのような通行権が設定されているのかを、売主から詳しく事情を聞くことが肝心です。といいますのも、これまで通路として利用できたという場合には、多くのケースで、地主の封鎖行為が違法な場合が多いからです。
そこで、まずは、通行権の種類についてご説明します。
① 通行地役権(物権的通行権)
これは売主と当該通路部分の地主との間において、売主の土地の便益のために、当該通路部分の土地を通行目的のために利用するという内容の地役権設定契約(民法280条)が締結されていた場合に生ずる権利です。
明確な地役権設定契約がなくても、10年以上にわたり、通路としての公然と使用し続けている場合には、通行地役権設定の時効取得が認められる場合もあります。
また、例えば、かつて袋地だった土地を地主が売主に分譲したという経緯がある場合には、公道まで通じる部分を通路として利用することを黙示に設定していたとして、通行地役権が認められる場合もあります。
通行地役権は、土地に登記することが認められる権利であって、登記がされていれば、たとえ通路部分の所有者が変わったとしても、その者に対し、通行地役権を主張できます。
② 通路利用契約(債権的通行権)
当該通路所有者との間において、通行を目的とする当該通路の利用契約が結ばれている場合にも通行権が発生します。
通行の対価を伴うものであれば、賃貸借契約ないしこれに類似した債権契約と考えられ、無償利用であれば、使用貸借契約ないしこれに類似した債権契約と考えられます。
債権的通行権の場合には、通行地役権と異なり、契約当事者間のみにおいて拘束力があるにすぎません。
したがって、債権的通行権の場合には、事前に、売主が買主に通行権を承継することを地主に申出て地主から承諾を取っておくことが必要になります。
したがって、債権的通行権の場合には、本問のように土地の売買が為されても、当然に、買主は売主が有していたこの種の通行権を主張することはできません。
④ 囲繞地(いぎょうち)通行権
購入した土地が他人の土地(囲繞地)に囲まれて公路に通じていない袋地である場合は、民法211条の囲繞地(いぎょうち)通行権として、その他人の土地を通行することができます。ただし、通行の場所および方法は、通行権者のために必要にして囲繞地のために最も損害の少ない経路でなければなりません。
したがって、本問においても、当該通路が当然囲繞地通行権の認められる通行部分であれば、すなわち、「通行権者のために必要にして囲繞地のために最も損害の少ない経路」であれば、囲繞地通行権が認められます。
他の囲繞地も含めて公道へ通じるより短い適当な通路があるようであれば、その通路の方に通行権が認めら、本件の当該通路には囲繞地通行権は認められません。
なお、建築基準法上、建物を立てるには敷地が原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(42条、43条)が、囲繞地通行権による通路の幅員としては、必ずしも2メートル以上の幅員が確保されているわけではありませんので、注意が必要です。
また、購入した土地が従前袋地でなかった場合は、分割されて袋地になったときの分割者の土地のみを通行できるだけです(民法213条)。
また、購入した土地の隣地が元々買主の土地であり、その土地が公道に面している場合にも、買主は、自分の土地を通行すればよいわけですので、囲繞地通行権は認められません。
⑤ 建築基準法上の位置指定道路・みなし道路
また、建築基準法上の位置指定道路或いはみなし道路として認められているケースも多くあります。
建築基準法上、建物を立てるには敷地が原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(42条、43条)。
建物建築のための接道要件といわれるものですが、それを満たすために、当該土地所有者等が特定行政庁に対し、この道路位置指定を申請し、これによって認められた道路が位置指定道路です。
また、4メートル幅以上の道路でないにしても、昭和25年11月以前という古い時期から現に建築物が建ち並んでおり、通路として使用されていたところは、特定行政庁が建築基準法上の道路とみなしている場合が多く、それをみなし道路(2項道路ともいいます)と呼んでいます。
このように当該通路部分が位置指定道路やみなし道路だとすると、そこに建築物を築造することはできず、本件の買主は当該通路を自由に通行できます。
2 本件では、まずは、上記のいずれの通行権が存在するのかについて、売主Aから詳しく事情を聞き、建物の建築確認申請時の資料を取り寄せたり、或いは、登記簿謄本、公図、地積図、旧土地台帳、航空写真などを取り寄せる、区役所の細街路課に問い合わせるなどによって、調査する必要があります。
その上で、通行権が存在する場合には、当該通路部分の地主に対し、構築物撤去を求める裁判を提起することができます。
仮に、調査の結果、通行権というものが認められなかった場合や訴訟をしても通行権の主張が認められなかった場合には、売主Aに対して、瑕疵担保責任に基づく契約解除、錯誤無効による契約の無効主張をすることになります。