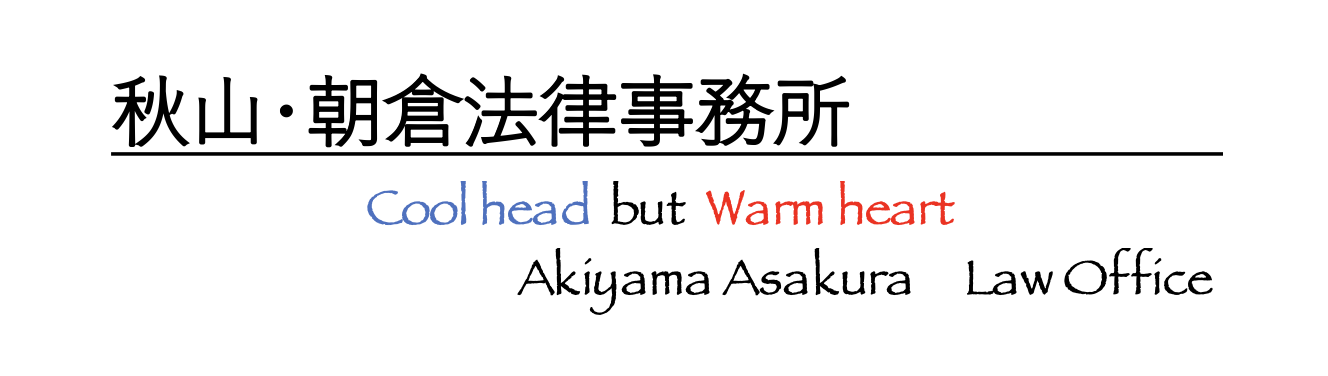借地権付建物を競売により取得する場合の注意点
<質問>
私は、借地権付建物を競売により取得しました。
落札後、地主のところに行き、改めて借地契約の締結をしたい旨を話しましたところ、地主は、承諾料として借地権価格の1割を支払わなければ借地権譲渡は認めないと言ってきました。
しかし、この競売物件の物件明細書には、借地人が借地上に建物を建てた際に地主が金融機関に提出したものと思われる借地上の建物に対する抵当権設定の承諾書が添付されており、その承諾書には「将来第三者が所有権を取得したときは、借主に対するもの同一の条件で、その者に引続き貸与します」と記載されており、地主の署名捺印が押されていました。
この同意書によると、地主は、借地権の譲渡について、事前に承諾しておりますので、改めて借地権の承諾料を支払わなくてもいいのではないかと思います。
このまま地主の同意を得ないでいても、地主に対し、借地権を主張することは出来るのでしょうか。
<回答>
1 まず、上記のような承諾書がない一般的な場合についてご説明致します。
競売により借地上の建物を取得した者は、建物の所有権と共に借地権も取得しますが、この借地権は地主の承諾を得て取得したものではないため、落札後に地主の承諾を得ないと、借地権の無断譲渡によって借地契約を解除されてしまいます。
そこで、借地借家法第20条は、競売によって借地権付建物を取得した借地人を保護するため、地主の承諾に代わる裁判所の許可の審判を申立てることができるとされております。
この許可の審判の申立てがあると、裁判所は、地主から介入権の行使があった場合や借地人が借地を暴力団事務所に使うなどの特段の事情がない限り、許可の審判を下します。ただし、自己の意思に関わりなく、借地権譲渡を認めなければならない地主の利益に配慮して、借地権価格の1割に相当する金員を借地権者が地主に支払うことが条件とされます。
2 ところで、上記の借地借家法20条の審判申立は、借地人が競売代金を納付した日から2ヶ月以内に申立てなければならないとされており、これは、当事者間の合意によって伸長することができない不変期間だとされております(東京地方裁判所平成10年10月19日判決・判例タイムズ1010号267頁)。
この2ヶ月の不変期間を設けた趣旨は、自らの意思に関わりなく借地権譲渡への承諾か介入権行使かを迫られる地主側の不安定な状態を速やかに確定するためとされております。
したがって、この期間を経過してしまうと、結局、競売によって借地権を取得した借地人は、地主に対し、借地権を対抗できなくなってしまい、地主の土地明け渡し請求に応じなければならなくなってしまいます(前記東京地方裁判所平成10年10月19日、東京高等裁判所平成17年4月27日判決)。
このような結論は、借地人に対しあまりにも酷なように思え、上記裁判例に対して批判の声もありましょうが、借地借家法20条の申立期間を経過した借地権者に対する裁判例の態度は厳しい傾向にあるようです。
なお、地主の土地明け渡し請求に対して、借地権を対抗できなかった借地人は、借地権を喪失することになりますが、裁判所は、そのような不利益も、借地借家法第14条に基づく建物買取請求権によって調整が図れるとしております。建物買取請求権を行使した場合に、地主が支払うべき建物代金には借地の場所的利益を金銭に換価したものも含まれますが、借地権価格と比べれば格段にその金額は低くなります。前記の東京地方裁判所平成10年10月19日判決は、場所的利益の金額を更地価格の1割として認定しておりますが、借地権価格が更地価格の7割前後であることに照らせば、借地借家法20条の申立期間を経過してしまったために、借地権付建物を競落した借地人が被った損失は極めて大きな額になります。
3 さて、以上を踏まえて今回のご質問ですが、確かに地主の承諾書を読めば、地主は借地権譲渡を事前に承諾しているように思えます。
しかし、東京高等裁判所平成17年6月29日判決(判例タイムズ1203号182頁)は、当該承諾書が提出されたのは競売物件の買受申出時から10年前であり、抵当権者に対して提出された書類に過ぎないことから、競売手続当時に承諾書の拘束力を有することを認めることが困難であるという理由で、借地権譲渡に対する地主の承諾を否定しました。
そして、当該事案では、既に借地借家法20条の申立期間を経過してしまった事案であり、また、地主側も競売の物件明細書や競売後の事前の交渉段階から借地権譲渡に対し承諾せず、介入権を行使する予定である旨を明言していたこと、借地権者側も不動産業者であり前記申立期間を徒過した場合に自らが被るリスクを認識し得たことなどの事情も考慮して、借地権を地主に対抗できないとの判断を示しました。その結果、結局、借地権者は、借地権が消滅したことを前提に建物買取請求権を行使しておりますが、借地権価格が億単位であったため、この事案の借地権者側の損失はまさに億単位のものになりました。
この裁判例の結論に対しても、学者の判例評者でも疑問が呈されておりますが、借地借家法20条の申立期間を経過した借地権者に厳しい態度を取っている点では、従前の裁判例の流れをつぐものと言えます。
4 本件でも、地主と交渉してみるにしても、代金納付日から2ヶ月以内に借地借家法20条の審判申立をしなければ借地権そのものが消滅してしまう可能性が高いことに留意する必要があります。うっかり地主と交渉している間に上記の期間を経過してしまうと取り返しがつきませんので、地主の承諾が得られなそうな時や承諾料の金額で争いがある場合には、速やかに、借地借家法20条の審判申立をすべきでしょう。
本件では、まずは上記の申立をした後に、借地非訟手続きの中で、前記の金融機関への承諾書をもって、承諾料の支払いなく許可をすべきである、或いは、承諾料の減額をすべきであると主張をすればよいと考えられます。